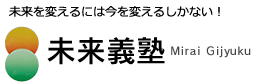学年順位を上げるために絶対にやるべき勉強法とは?『学年順位1ケタの先輩たちが実践する成績アップの秘訣!』

明日からスタートする、期末テストに向けて、
昨日に続き今日もテスト勉強会を午前中から実施。
今日の午前中は、生徒一人ひとりの学校のテキストをチェックしつつ、
テスト勉強に関するアドバイスをしました。
今日は、学校のテキストを使った勉強の仕方についてブログで綴ってみたいと思います。
学校テキストを徹底的にやり直した人が、成績を上げている!

テストで結果を出している生徒、
毎回順位を上げている生徒には、大きな共通点があります。
その共通点とは、特別な勉強法をしているわけではなく。
彼らは、必ずテスト範囲を3回以上繰り返して解くということです。
つまり、同じ問題を繰り返して解くということが成績を上げる最大のコツだということ。
卒塾生で、学年順位が1ケタを取っていた先輩達は、
同じ問題を4~5回解くのが当たり前でした。
さすがに、やることが半端ではありません。
しかし、このことからも手を広げず同じ問題を繰り返し解くことが重要だと分かるはずです。
テキスト1回目は、仕分け!

テキストを解く1回目は、
自分の理解している問題と理解していない問題を仕分けるために行います。
自分ができない問題はどれか?わからない問題はどれか?
それをはっきり認識するために行うのであって、
1回目は、テストで良い結果を出すための準備にしかすぎません。
仕分けをしたからといって、
できなかった問題ができるようになるわけではないからです。
本当の勉強は2回目から。

できなかった問題をできるようにするのが2回目であり、
さらにそれを深く理解するのが3回目です。
だから、テスト勉強で大切なのは、2回目以降となります。
例を上げて話すと、数学のテスト範囲を見てみると、
数学の友(テキスト)
数学の基礎練習(計算プリント)
配布プリントや補助教材などです。
上記で最初に解くのは、「数学の友」です。
特に日頃宿題になっていなくても、学校の授業で学習した単元は、自分で解いていきましょう。
直接、テキストに解くのいいのですが、ノートに一度解いておいて、
テスト前に直接テキストを解いておくとよい復習になります。
その時に、間違えた問題や分らなかった問題は、
必ず問題番号に印や付箋などを付けておいて、
2回目、3回目のやり直しの時に、
どの問題をやり直しすべきなのかスグに分るようにしておくことですね。
「解ける!」「わかる!」と実感できる3回目!

定期テストで順位を大幅に上げている生徒達に、
「テキストは、何回やり直しをしますか?」と聞くと、必ず「3回以上!」と答えます。
「なぜ、3回以上やるの?」と質問すると、
全員「だって、3回以上やらないと覚えることができない!」と口を揃えて答えます。
つまり、テストで結果を出している生徒ほど、
繰り返し解かないと覚えることが出来ないと分っているのです。
但し、「3回やればいいんだ!」とばかりに、これまた作業にしてしまう生徒がいます。
作業にしてしまうと、数学など答えのみを覚えてハイ終了なんて生徒もいます。
当然、答えだけ覚えてもテスト本番で解くことはできませんよね。
やり方そのもを根本的に理解しているわけではないからです。
そういった意味で、やり直しの2回目、3回目は、答えを見ながら解いてはいけません。
問題文だけを見て、自分の力で解くことが大切です。
その時、自分で解けそうもなかったら、まずは、解答・解説を読みマーカーなどで線を引きましょう。
必要があると思えば、ノートに解説。
解答を自分の言葉に直して書いてみましょう。
充分理解出来たら、もう一度ノートに解説・解答を隠して、もう一度解いてみる。
それでも解けない問題は、必ず先生に質問して教えてもらいましょう。
質問した問題も、問題番号に印を付け、付箋を付けておくとよいと思います。
後から、もう一度やり直しをする時に、役立ちます。
今日は、テスト前の勉強方法をお伝えしました。
是非、役立ちそうなら参考にしてみて下さい。

『NEVER STOP LEARNING』学ぶことをやめないで!
塾の先生として、教育者として35年間変わらず子供達に伝えてきた想いがあります。できるだけ多くの子供達に、この『NEVER STOP LEARNING』学ぶことをやめないで!というメッセージを届けたくて、今回映像クリエイターに撮影を依頼して、MV(メッセージビデオ)を作成しました。
お母さん、お父さん。保護者の皆さん!是非、お子さんと一緒にこのMVを見て頂ければと思います。そして、見て頂いた後に、お子さんと一緒に「なぜ、勉強するのか?」お子さんの未来を変える、可能性を拡げるための「学び」の本質について、話をする機会を持って頂ければと思います。
(PS)MV開始、30秒あたりから音声が小さくて聞き取りずらくなります。外での撮影で声が上手く録音できませんでした。聞き取りずらい場合は、少しボリュームを上げて視聴下さい。
『高校入試の分析と予想』わかりやすく、楽しく動画解説。
『受験生を持つママたち、そして、受験生諸君に愛知県公立高校入試について、できるだけわかりやすく、そして楽しく伝えたい!』そんな熱い想いを個性的な二人の塾長達が、タッグを組んで動画を作りました。受験について考える際に少しでも役立てば嬉しいです。
5科目合計平均点が過去最高の300点を越えた愛知県公立高校入試。 コロナの影響で、ここ数年中学校などにおいて臨時休業が実施されたことを踏まえ、基礎的・基本的な事項をより重視して出題するとされていた影響で平均点が上昇。 そして2023年は、初めて全面的にマークシート方式が採用され、記述解答が一切なくなった。 ある程度平均点は上がると考えていたが、予想を遥かに超えてここまで上がるとは。 県内で最も入試問題や情報に詳しい経験豊富な塾長二人がわかりやすく、そして楽しく動画解説しています。
2023年度愛知県公立高校入試の数学 マークシート方式が採用されたが、問題構成は昨年と同様。 大問3のみ数値をマークする形式で、2点問題はグラフの活用の1問。 しかし、その難易度は、大幅に易化した。 平均点は、22点満点中 15.2点 100点換算すると、69.1点。 この点は、過去に例のない高さになった。 前編で説明していない、各科目の難易度や来年度の予想を県内で最も入試問題や情報に詳しい経験豊富な塾長二人がわかりやすく、そして楽しく動画解説。
守田 智司
最新記事 by 守田 智司 (全て見る)
- 妻と娘が祝ってくれた還暦、名古屋の美登利寿司で美味しいひととき! - 2024年7月20日
- 自分の子供を留学させた塾長が語る、親のための留学ガイド【プロローグⅡ】 - 2024年7月19日
- 自分の子供を留学させた塾長が語る、親のための留学ガイド【プロローグⅠ】 - 2024年7月18日
- 『フライパンには戻れない!』肉汁溢れる!グリルで楽しむ生ウインナー (〃)´艸`)ウマウマ♪ - 2024年7月14日
- 令和7年度愛知県公立高校入学者選抜 【各高校校内順位の決定方式】発表!※進学校 Ⅲ→Ⅴ型に変更が目立ちます! - 2024年7月13日